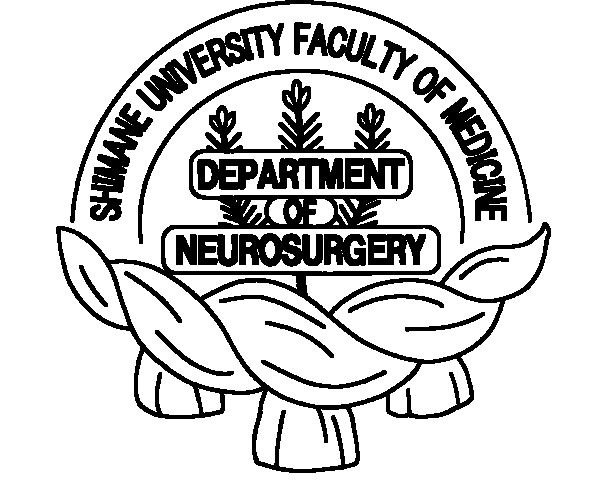ホーム > 患者さんへ > 診療内容・実績 > 小児脳神経外科
小児脳神経外科
脳の病気を持つお子さま、またご両親・ご家族に安心してお過ごしいただけるよう診療致しております。特に小さなお子さまは、大人とは体の作りが大きく異なるため、診断・治療に関しては専門的な知識が求められます。
当院は日本小児神経外科学会認定医が常駐し、また小児科と密な連携を取りながら、お子さまとご両親・ご家族に推奨される治療方法をお伝えし、ご希望に沿った治療が行えるよう努めております。
主に次のような病気に対して診療を行っておりますが、それ以外の病気に対しても他院と連携を取りながらご対応致しております。
| 脳腫瘍 | 脳血管障害 |
| 水頭症 | 二分脊椎 |
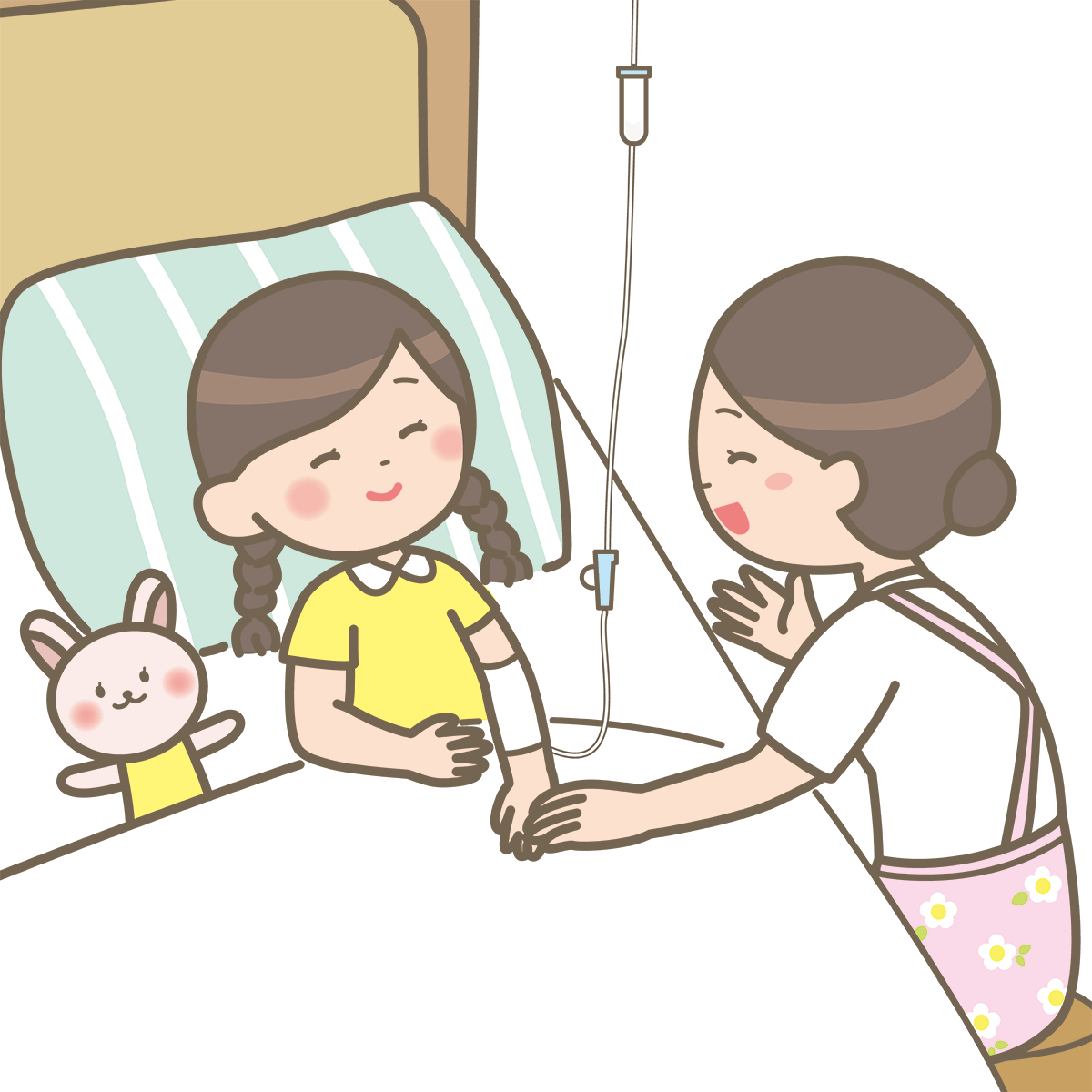
【脳腫瘍】

小児の脳腫瘍は成人と同様で稀な病気であり、人口100万人あたり年間6~7人と報告されています。代表的な小児の脳腫瘍は、神経膠腫、胚細胞腫瘍、髄芽腫、頭蓋咽頭腫、上衣腫があります。
小児脳腫瘍の難しいところは成人と異なり自覚症状が明確でないため、頭の検査を受けるまでに時間がかかることです。画像検査で発見されたときには既に巨大な腫瘍になっていた、ということもよく経験します。
小児脳腫瘍の概要をご説明いたします。
[ 症状 ]
次のような症状があるときは注意が必要です。
①頭痛
新たに発生した持続する頭痛(4週間以上)があるとき
※乳幼児では頭痛の訴えができないため観察が必要です。
②嘔気・嘔吐
2週間以上続くとき
③眼科的異常
2週間以上続くとき
ここでの「眼科的異常」とは、視力低下や視野障害、眼球運動異常などです。
眼科の先生にとっては視神経乳頭の異常が重要になります。
④成長・発達障害
思春期遅発、思春期停止、多飲・多尿 など
⑤行動異常
嗜眠がみられることがあります
⑥運動機能
これまで見られなかった異常が2週間以上続くとき、退行がみられるとき
[ 診断 ]
頭部CT・MRI検査を行い、必要があればカテーテル検査なども行います。
確定診断には腫瘍の摘出術を行うことが必要になります。小児の脳腫瘍は術前後の化学療法と放射線治療が極めて重要であり、摘出した病理組織による診断結果によって行う内容が決まります。近年では、腫瘍組織の遺伝子診断を行うことでより効果的な治療法が選択できるようになりました。
[ 治療 ]
①手術(摘出術)
一部の小児脳腫瘍を除いて、基本的には摘出術が最も重要な治療となります。そのため、全摘出・可及的摘出を目的とした手術戦略を立て、実行するために必要なモダリティーを用意して治療を行います。
②化学療法
手術摘出のみで治癒可能なものを除いて、放射線治療と並んで重要な治療が化学療法です。
子供の場合は放射線治療に伴う放射線被ばくにより成長発達障害や認知機能障害、もやもや病などの血管障害や二次性腫瘍の発生などの有害事象が問題となります。これを極力避けるために放射線治療の強度を下げざるを得ず、その治療分をカバーするためにも化学療法は極めて重要と考えられています。
根治を目指すため、強力な化学療法を行いますが、そのために白血球や赤血球など生きるために必要な細胞が低下し重篤な感染症などを起こすことがあります。これらを予防するためには極めて専門的かつ高度な子供の治療体制が必要であり、当院では小児科と協力して治療を行わせて頂いております。
③放射線治療
小児脳腫瘍の中には放射線治療が効きやすいものが多く、重要な治療法である。ただし、先に述べたように放射線による有害事象を避ける必要があり、化学療法の併用を行うよう工夫しております。
また摘出術や化学療法が終えた後に、県外になりますが本邦有数の放射線治療施設へ治療目的に御紹介させて頂くこともあります。
【脳血管障害】
小児の脳血管障害は、成人と同様に虚血と出血に分けられますが、成人の病気とは成り立ちが異なることが多く、また小児特有の病気も存在します。そのため、成人とは異なる治療戦略が必要になることもあります。
特に代表的な小児脳血管奇形であるもやもや病と頭蓋内動静脈短絡疾患について概要をご説明いたします。
[ もやもや病 ]
もやもや病は内頸動脈という脳全体の約2/3を栄養する血管が、進行性に狭窄・閉塞し、代償として異常な血管網の発達(もやもや血管)を認める原因不明の病気で、家族性に発症することが知られています(約10%)。
幼少期は脳の血流が悪くなるために脳梗塞やその前兆とされる一過性脳虚血発作を呈して発見されることが多いですが、その他には頭痛や発達障害で発見に至ることもあります。
特に熱いめん類などの食べ物を食す際のフーフーと冷ます動作や、吹奏楽器の演奏、息がきれるような運動や激しく泣くことなどが引き金となって脳虚血症状が出現することが特徴です。
脳虚血症状を呈したり、脳出血がもやもや血管に原因があると考えられた場合に手術加療(血行再建術)を検討します。
無症状の場合は、病状が進行することがあるため治療を行わない場合も慎重な画像検査によるフォローを行います。
詳細は もやもや病のページ を参照ください。
[ 頭蓋内動静脈短絡疾患 ]
小児の頭蓋内動静脈短絡疾患は、ガレン大静脈瘤など多数ありますが、臨床像は疾患に関係なく症状のでる時期により特徴的な症状を認めます。
・時期と症状の特徴
①新生児:重篤な心不全
②新生児~乳児期:軽度~中等度の心不全と頭位拡大で発症するもの
③乳児期(~2歳):水頭症と痙攣発作
④年長児~成人:頭痛や精神発達遅滞,痙攣,脳出血で発症するもの
⑤稀ではあるが,静脈瘤が血栓化し自然消褪することもある.
・治療と予後
未治療の場合は、極めて予後が不良であるため、症状を認め、診断がついた場合は積極的な加療が推奨されます。特に血管内治療が現時点では最善の方法と考えられています。
ただし、新生児は非常に血管が脆いため,血管内治療自体が合併症を作る可能性が高く、軽症の心不全であれば内科的治療で管理し、患児の成長を待ってから加療を行うことがあります。
待てない場合は,救命目的の加療となります。
【水頭症】

水頭症とは、脳脊髄液が脳室やくも膜下腔に異常に溜まってしまう病気です。
子供の場合は、後天的なものと先天的(生まれつき)なものがあります。
後天的なものとして、代表的な原因疾患は脳腫瘍や外傷、出血や感染が挙げられます。
先天的な水頭症の原因として、嚢胞や二分脊椎といった脳神経系の形成段階での病気が代表的です。中には母親の感染症が原因となって、脳神経の形成がうまくいかずに水頭症を生じてしまうこともあるため、母親の検査は重要なものと考えます。
症状は年齢と共に変化しますが、小児の水頭症の特徴として痙攣発作を合併することがあります。
[ 時期と症状の特徴 ]
①低出生早産時
無呼吸、徐脈、大泉門の膨隆、頭皮の静脈の怒張、球状頭蓋、頭囲拡大
②新生児・乳児
①に加えて、嘔吐・傾眠、頸のすわりの遅れ、眼球運動異常
③幼児・学童
頭痛、嘔吐、傾眠、複視、鬱血乳頭、腱反射の増強など
[ 治療と予後 ]
小児水頭症の治療の目的は、水頭症による脳の損傷を最小限に抑えられるように治療を行い、最良の発達を促すことです。そのため、治療が望ましい状態と判断された場合には出来るだけ早期の治療を行います。
治療方法は手術加療が基本となりますが、感染症や腫瘍などが原因と考えられる場合は、その治療が優先されます。
①シャント術
最も一般的で有効な治療方法です。
過剰な髄液をチューブを介して腹腔や心臓へ誘導し、体循環に戻すことで頭蓋内環境を正常な環境にすることを目的としています。この治療方法は半世紀前から行われ、近年はデバイスも改良されているため、安定した治療効果が得られますが、治療の性質上異物が常に体内に残るため、シャント感染や、シャント閉塞、成長に伴うチューブの逸脱、髄液過剰排液などが問題になることがあります。
②神経内視鏡手術
内視鏡的第三脳室開窓術が代表的な治療法です。
内視鏡手術は身体に異物となるシャントデバイスの留置が必要ないため、異物感染や髄液の過剰排液といった合併症が避けられる利点があります。ただし、一方で脳出血や神経損傷、術後の安定期に開創部が閉塞することで生じる急激な頭蓋内圧上昇による死亡例など予期せぬ合併症が報告されているため、行う場合は十分な検討が必要です。
詳細は 神経内視鏡治療のページ を参照ください。
シャント術、神経内視鏡手術ともに治療成績に差はなく、両治療ともに10年程度で約半数の方が閉塞した、と報告されており、治療後も定期的な外来でのフォローが重要になります。
【二分脊椎】
二分脊椎とは脊椎骨の骨癒合不全を示す言葉であるが、原因は脊髄の形成異常によることがわかっています。
二分脊椎は脊髄組織が表皮に覆われずに外表に露出している開放性と、露出していない閉鎖性とに分けられます。
開放性二分脊椎の代表的な病態として脊髄髄膜瘤が挙げられます。
閉鎖性二分脊椎の代表的な病態として脊髄脂肪腫や先天性皮膚洞、割髄症、肥厚終糸といった病気が原因となって生じます。
それぞれの概要をご説明します。
[ 開放性二分脊椎(脊髄髄膜瘤) ]
典型的な所見は、腰部の皮膚欠損とその部位から脊髄が露出していることです。
主な症状として、足の麻痺、膀胱直腸障害、軽度学習障害が挙げられます。
また水頭症とキアリ奇形という病気を高率に合併し、それぞれに対して治療が必要になることがあります。
生後48時間以内の手術加療が推奨され、出生前から診断がつくため、産婦人科との連携が不可欠な病気です。
予防法として母親の妊娠前(妊娠1カ月前)からの葉酸の摂取が重要です。また抗てんかん薬を内服されている場合は種類によってはリスクとなるため、計画的な薬剤変更などが大切になります。
[ 閉鎖性二分脊椎 ]
開放性二分脊椎のように外表面に明らかな異常所見を認めることはなく、成長とともに神経症状が出現し、発見されることが多い病気です。
主な症状として、歩行障害や膀胱直腸障害、腰~足にかけての痛みなどがあります。
皮膚の所見としては、腰部に皮膚の凹みや多毛などを認めることがあり、診断の一助になることがあります。
症状は就学時期に出現することが多いですが、例外もあります。